基調講演
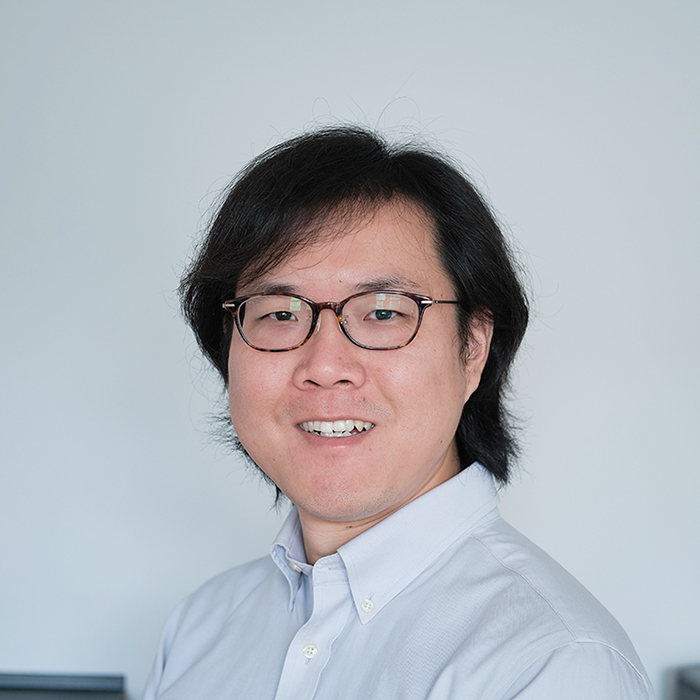
Gabriel (Naiqi) Xiao, Associate professor
McMaster University, Canada
通訳
鶴見 周摩 北海道大学 助教
カナダの新進気鋭の赤ちゃん研究者であるGabriel (Naiqi) Xiao准教授(マクマスター大学)に、乳児の知覚発達における学習と記憶の役割についてご講演いただきます。
(講演の日本語概要)
本基調講演では、「知覚の発達」が単なる感覚の成熟ではなく、学習や記憶といった高次の認知システムと密接に関わっていることをお話しします。これまで、赤ちゃんの知覚発達は目や耳などの感覚が徐々に発達していくと言われていましたが、赤ちゃんは生まれたときから「学習」や「記憶」の力を使って、周りの世界を理解しようとしていることがわかってきました。最近の脳画像研究や行動実験の結果をもとに、赤ちゃんが文脈や予測に基づいて柔軟に世界を知覚し、経験に基づいた学習戦略に大きく影響されていることを紹介します。赤ちゃんの知覚が受動的な感覚処理ではなく、経験を通して能動的に形成されているという新しい見方を提示し、このような知覚と学習の相互作用の理解から、認知発達の根本的な仕組みを明らかにする手がかりを提供します。
講演題目
Beyond Sensory Refinement: The Crucial Role of Learning and Memory in Early Perceptual Development
講演概要
Perception, a fundamental cognitive capacity, undergoes rapid development within the first year of life, often characterized by its adaptation to environmental factors. This developmental trajectory, particularly phenomena like perceptual narrowing in infancy, has traditionally been attributed primarily to changes within the perceptual systems themselves, often conceptualized through feedforward models of sensory refinement. This keynote challenges this established view, proposing a significant advancement: the early and integral involvement of learning and memory systems in shaping perceptual abilities from the outset.
While models emphasizing unidirectional sensory processing have been influential, emerging evidence, fueled by novel methodologies, points towards a more dynamic interplay. Neuroimaging techniques, for instance, reveal that learning can modulate infants' sensory responses from birth. At the behavioral level, studies utilizing rapid, single-trial assessments demonstrate that visual perception in infancy is rapidly and flexibly modulated by contextual predictive cues. Furthermore, this involvement of learning is itself profoundly shaped by experience with specific learning strategies becoming crucial in determining how infants perceive salient stimuli, such as faces. This body of work indicates that even preverbal infants’ perception is not solely a reflection of sensory input but is actively and continuously shaped by their learning history.
Therefore, this talk will argue that perceptual development is not simply a refinement within perceptual areas, but rather an experience-dependent calibration of the interaction between perceptual and higher-level cognitive systems. This reconceptualization moves beyond a purely sensory-driven account, highlighting how infants actively leverage learned information to navigate and make sense of their complex sensory world from the earliest stages. Understanding this interaction between perception and learning opens new avenues for investigating the foundations of cognitive development and the adaptive mechanisms shaping early human experience.
経歴
Dr. Gabriel Xiao is an Associate Professor and University Scholar (2025-2029) at McMaster University, Canada. A leading expert in infant perceptual and cognitive development, he previously held a Canada Research Chair (Tier II, 2020-2025). Dr. Xiao's research investigates how early experiences and learning mechanisms shape perception in infancy, particularly exploring the interplay between sensory processing and developing cognitive systems like memory and attention. Utilizing innovative methods such as eye-tracking and infant neuroimaging, his work has garnered significant support from national funding agencies including the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), as well as multiple internal university funds. Published in top-tier journals, Dr. Xiao's research on fundamental cognitive development offers crucial insights into early human learning and perception, while also illuminating the developmental roots of important social issues, such as the emergence of social biases.
大会企画シンポジウム①
テーマ名
XR(クロスリアリティ)環境のなかでの乳幼児の発達を考える
企画代表者
七海陽(相模女子大学学芸学部子ども教育学科 准教授)
司会者
七海陽(相模女子大学学芸学部子ども教育学科・准教授)
企画趣旨
乳幼児が触れるメディアや遊ぶ環境にXR(クロスリアリティ)が混在してきている。図鑑にはAR機能が付き、スマホをかざして見ると家の中に動物や魚などの立体映像が現れる。タブレット端末のお絵描きARアプリで絵を描けば、命を宿したように動き出す。屋内のプレイグラウンドでは、身体の動きにインターラクティブに反応するプロジェクションマッピングの世界で遊ぶことができ、映像に連動して立体音響が聞こえたり、床面が振動したり、風や匂いを感じたりできるなど、触覚や嗅覚などの諸感覚を提示するXR技術によるイマーシブ体験も可能になってきた。しかし、環境との相互作用により発達している乳幼児が、生活や遊びでXRを経験することが発達にどのように影響するのかは明らかになっていない。社会はよりフィジカルとサイバー体験とがシームレスになっていくと予測されるため、今、発達過程にある乳幼児がXRに何を感じ、どのように認識しているのかなど、認知発達における知見を蓄積していくとともに、研究方法論についても検討する必要があると考える。そこで、先駆的な研究について話題提供していただき討論を行うことで、本テーマに関する議論を深め、今後の展望について考えたい。
話題提供者
白井述(立教大学 現代心理学部 心理学科 教授)
宮崎美智子(大妻女子大学 社会情報学部 准教授)
河合隆史(早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 教授)
指定討論者
長井 志江(東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授)
大会企画シンポジウム②
テーマ名
赤ちゃん×ロボット
企画代表者
石原尚(大阪大学大学院工学研究科 准教授)
司会者
石原尚(大阪大学大学院工学研究科 准教授)
企画趣旨
ロボットは日常生活で身近になりつつあり、ロボットという情報メディアと赤ちゃんの関係を理解するための研究はますます重要となってきています。一方で、赤ちゃんという存在自体も、周囲の人々の繋がりを色濃くする媒体(メディア)として重要であり、赤ちゃんのどのような特性が有効に働いているのかは興味深く、また未来の情報メディアの在り方を考えるうえでも重要です。このシンポジウムでは、「赤ちゃん×ロボット」をテーマとして3名の研究者が話題提供となる講演を行った後、赤ちゃんというメディア、そしてロボットというメディア、それぞれの捉え方や組み合わせ方についての課題や展望についての理解を深める議論を行います。
話題提供者
奥村優子(NTTコミュニケーション科学基礎研究所 主任研究員)
小坂崇之(東海大学情報理工学部 准教授)
石原尚(大阪大学大学院工学研究科 准教授)
指定討論者
浅田 稔(大阪大学 名誉教授・特任教授、大阪国際工科専門職大学 副学長)
特別企画シンポジウム
テーマ名
赤ちゃんを見守る家族にできること
子育てケアラー・ヤングケアラーへのウエルビーイングを目指したCOI-NEXT・RISTEXの取り組み
企画代表者
門田行史(自治医科大学ヘルスエクイティ地域共創センター/小児科 副センター長/准教授)
司会者
高瀨堅吉(中央大学文学部教授)
企画趣旨
本企画は、赤ちゃんを見守る家族および子育てケアラー・ヤングケアラーを対象とした支援体制の構築を目的とし、COI-NEXTおよびRISTEXにおけるビジョンと成果を紹介するものである。近年、ケアラーの心身的・社会的負担の軽減は喫緊の課題であり、「ケアする人をケアする」視点が重視されている。シンポジストの門田は、科学技術と地域資源を融合させた持続可能な支援モデルの確立を目指し、エビデンスに基づく介入の最適化を図るCOI-NEXT・RISTEXの概要を紹介する。伊藤氏は、「生誕1000日見守りプロジェクト」において、赤ちゃんの情動や行動指標を解析し、保護者が適切な対応を実施できるAI支援型アプリケーションの開発について報告する。中井氏は、赤ちゃんの気持ちが分かり、ケアする側が適切な対応をとることができるアプリの開発・実装について紹介する。高瀬氏は、本プロジェクトを結びつける人と人とのつながりの視点から、シチズンサイエンスの手法を取り入れた取り組みを紹介し、出産・育児期におけるウェルビーイングの向上および地域社会における包括的ケア支援の新たな社会実装の在り方について議論する。
話題提供者
門田行史(自治医科大学ヘルスエクイティ地域共創センター 副センター長)
高瀨堅吉(中央大学文学部 教授)
伊藤雄一(青山学院大学 理工学部情報テクノロジー学科 教授)
中井洸我(株式会社クロスメディスン 代表取締役・CEO)
音楽部会企画ラウンドテーブル
テーマ名
赤ちゃんからの音遊び、楽器遊び―赤ちゃん学から考える音楽表現カリキュラム―
企画代表者
村上康子(共立女子大学 教授)
司会者
村上康子(共立女子大学 教授)
企画趣旨
音楽部会では2023年から連続して、主に1歳児を対象に子どもの楽器とのかかわりについて研究を進めてきた。子どもが能動的に楽器とかかわり、楽器や音を介した他者とのかかわりを通して文化を学び、共に文化を担う存在となっていく姿を捉えてきた。さらに、子どもの行為を支える他者からの様々なかかわりを見てきた。しかし、保育現場における器楽活動の難しさは多くの保育者が感じているようである。一つの大きな課題は、一連の発表で紹介してきたような子どもの楽器とのかかわりと、いわゆる既存の楽曲を演奏するという行為との連続性の見えなさではないだろうか。一朝一夕で見える連続性ではないが、これまで観察した子どもの楽器とのかかわりの中に、いくつもの象徴的な局面もあったように思われる。その背景に様々な大人からの働きかけもあったように思われる。文化的実践者として音を扱う人へ、音にまつわる表現の育ちを丁寧に探りながら、カリキュラム化への示唆を得たい。
話題提供者
丸山愼(駒沢女子大学 教授)
今川恭子(聖心女子大学 非常勤講師)
伊原小百合 (玉川大学 講師)
村上康子(共立女子大学 教授)
乳児行動発達研究部会企画ラウンドテーブル
テーマ名
NICU入院児に対する発達支援にメディア(媒体)をどう活かせるか
企画代表者
儀間裕貴(東京都立大学大学院人間健康科学研究科 准教授)
司会者
儀間裕貴(東京都立大学大学院人間健康科学研究科 准教授)
企画趣旨
現代社会はメディア(媒体)を通じて提供される情報や表現に溢れており、そのコンテンツには映像系、音声系、テキスト系、インタラクティブ系(ゲームなど)、ソーシャルメディア系など多岐にわたる。無論それは子どもが育つ環境においても同様であり、子どもはそれらのメディアから何かしら発達に必要な刺激や情報を得ていると考えられる。
新生児期や乳児期初期の赤ちゃんにとって、メディアコンテンツから提供される情報や表現の意味を理解することはまだ難しいが、それを視覚刺激や聴覚刺激として受容しており、コンテンツの種類によっては嗅覚刺激や触覚刺激、前庭刺激なども複合的に受容している可能性がある。
本ラウンドテーブルでは、そのような感覚刺激の受容が不十分になりやすい、NICUで加療されている早産・低出生体重児に対する発達支援について考えたい。司会者と4名の話題提供者から、それぞれの臨床実践や研究成果に基づいた知見を示し、早産・低出生体重児やその家族の発達支援にメディアをどう活かせる可能性があるのかについて議論したい。
話題提供者
儀間裕貴(東京都立大学 理学療法士)
有光威志(慶應義塾大学 医師)
豊島勝昭(神奈川県立こども医療センター 医師)
江口理絵子(埼玉県立小児医療センター新生児科 音楽療法士)
浅野大喜(日本バプテスト病院 理学療法士)
保育実践科学部会企画ワークショップ
テーマ名
私たちは乳幼児のスマホ・タブレット使用のなにが怖いのか?
企画代表者
楢﨑雅(社会福祉法人摩耶福祉会幼保連携型認定こども園るんびにこどもえん 園長)
司会者
楢﨑雅(社会福祉法人摩耶福祉会幼保連携型認定こども園るんびにこどもえん・園長)
麦谷綾子(日本女子大学人間社会学部・教授)
企画趣旨
スマホやタブレット、コンピューター端末といったパーソナルデバイスは、私たちの生活において欠かせないものとなっており、それは子どもたちにとっても同様です。就学年齢の児童が1人1台の端末を所有し、学習に利用することを国を挙げて推進するGIGAスクール構想をはじめ、パーソナルデバイスの教育現場への導入が積極的に進められています。子育てにおいても、動画をはじめとするさまざまなコンテンツをオンデマンドで、赤ちゃんのころから視聴することは、もはや当たり前の営みになってきました。その一方で、子育てに関わる多くの人が、パーソナルデバイスの使用が子どもの発達にネガティブな影響を及ぼすのではないかと、漠然とした不安を抱いています。このワークショップでは、私たちが乳幼児のパーソナルデバイス使用において、具体的に何を「怖い」と感じているのかをあぶり出すことを目的とします。話題提供者によるミニレクチャーの後、グループに分かれてワークを行い、最後に可視化された「恐れ」を共有します。子育てに関心を持つ、さまざまなバックグラウンドを持つ方々のご参加を歓迎します。
※定員:24名(事前登録制)
登録フォーム
話題提供者
旦直子(帝京科学大学教育人間科学部 教授)
保育環境部会企画ワークショップ
テーマ名
音環境は子どもの居場所をどう変えるか? ― 研究報告とワークショップ
企画代表者
嶋田容子(同志社大学脳科学研究科 助教/赤ちゃん学研究センター 嘱託研究員)
司会者
嶋田容子(同志社大学脳科学研究科 助教/赤ちゃん学研究センター 嘱託研究員)
企画趣旨
保育環境部会では、子どもの姿に即して考え、エビデンスに基づき判断し、結果を子どもの前に戻すという双方向の取り組みを続けています。保育を考えるにあたっては「何をするか」からの出発ではなく「子どもたちの状況・興味関心は何か」など子ども理解から考えることが大切です。登壇者らが「音環境」に関する実証研究を共に進める中で、音がトリガーとなり遊びや活動が影響を受けた事例や、視覚的・体感的な経験の関わる事例が多く挙がりました。「音環境」×「そのほかの要素」で、子どもの興味関心をより喚起する環境構成が行えるかもしれません。
会の前半では、保育現場からの観察報告、音環境の改善を通じて現場が感じた保育の変化、その後に気づいた様々な観点から子ども理解がより深化する子ども理解の深化について模索し(岡部)、そしてこれらの可能性についてデビデンスに基づく検討を試みます(嶋田)。後半では、音環境の変化の中で生じた子どもの様子について事例を紹介し、フロアの皆さんもご一緒に「手立て」を自由に考えていただきたいと思います。研究者・実践者問わずどなたでもお気軽にご参加下さい。
話題提供者
嶋田容子(同志社大学 助教)
岡部祐輝(高槻双葉幼稚園・(一社)大阪府立幼稚園連盟 教育研究所 園長・所長)


